わたしは、自分の生徒さんたちのレッスンに「スズキバイオリン教本」を使うことがあります。
この教本って、初めは子供の童謡みたいなものばっかりなんですけど、1巻も最後の方になってくるとだんだん本格的な曲が現れてくるんですよね。
教えていて、「あああー、曲らしい曲を弾けるようになってきたなー」と、感慨深くなるのが13曲目に入っている、バッハのメヌエット。

そういえば、よく「メヌエット」ってタイトルの曲をよく見かけますよね。なんでこのタイトルの曲がたくさんあるんですか?
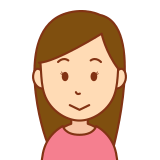
あ、確かについそう思っちゃいますよね。実はメヌエットって、曲のタイトルっていうよりはバロック時代の舞曲なんです。
そう。メヌエットってそもそも舞曲、つまりダンスのための音楽だったんです。
今日は、メヌエットを演奏するときに知っていると役に立つお話しをしたいと思います。
スポンサーリンク
メヌエットってそもそも何なの?
実は過酷だった舞踏会
メヌエット(Menuett)というのは、17~18世紀に有名だったダンスです。
フランスが起源で、一番初めのメヌエットは1670年ごろ、ルイ14世の宮廷で踊られたんだそうな!

1670年って、日本でいうとまだ江戸時代前期ですね。そのころヨーロッパでは宮廷で舞踏会ですか。。優雅ですねえ。
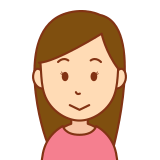
それが、実はそうでもないみたいなんですよ。
舞踏会っていうと、豪華な大広間できらびやかに着飾った貴族たちが、思い思い好きな人たちと楽しくダンスしているイメージありませんか?
でも実際当時の舞踏会って、王様や皇帝から呼びつけられて、「行かなければならなかった」ものだったんですって。

楽しそうなのに、みんな行きたくなかったんでしょうか?
当時の舞踏会って、好きな人と踊れるわけじゃなくって、もともと踊る人が指定されていたり、自分たちでリストに名前を書き込んでペアを決めたりしなければならなかったんです。
そのうえ、王様や皇帝たち以外の人は座る席もなく、食べ物もトイレもない始末。。。
しかも、メヌエットってみんなが一斉に音楽に合わせて踊っていい踊りではなくて、1組ずつ順番に踊る踊りなんです!
1組が踊り終わるまでに10分かかるとして、招待された貴族たちが何十組もいたりしたら。。。
それも立ちっぱなしでずーっと自分の出番を待ち続けなければならないとしたら。。。

全っ然楽しくないですね。断っちゃだめなんでしょうか。。
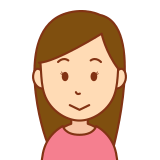
ルイ16世は、貴族を監視するための政策として舞踏会を催していたといわれるの。貴族に暇を与えず、危険思想を排除するのに有効だと考えてられていたのよ。

なんか日本の同時代にあった参勤交代みたいですね。
それでは、当時のメヌエットが踊られていた宮廷舞踏会の過酷さがわかったところで、それがどんな踊りだったか見てみましょう。
メヌエットってどんな踊りだったの?
メヌエットの名前の由来は「pas menu」、小さなステップという言葉から来ています。
メヌエットは男女のペアで踊るダンスで、先ほども書いたように1組ずつがみんなの前で踊りを披露することが普通でした。
ペアのそれぞれはまず部屋の対角線上に一人ずつ立ち、厳格に決められたステップを踏みながらZやSの形に部屋を移動していきます。
部屋の真ん中で二人が出会ったところで初めて一緒に踊り、そのあとはまた一人ずつステップを踏みながらZやSの形を続けて辿りながらスタートした部屋の対角線の場所に向かっていくものでした。

一人で踊ってる時間が結構長いダンスで緊張しそうですね
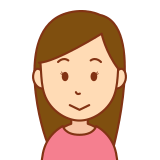
そうそう。しかも踊り方、劇ムズだったらしいですよ。すっごく練習しなければ踊れるようにならなかったんですって。
メヌエットを楽曲として演奏する上で知っておくべきこと
メヌエットには厳格に決められたステップがありました。
メヌエットの音楽は、そのステップに合わせて構成されています。
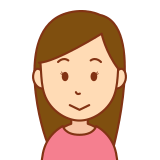
よく起こりがちなのが、3拍子だから1拍目を強調して1・2・3・1・2・3と常に1拍目を強調して弾いてしまう、という現象かしら。

だめなんですか?
メヌエットは2小節が1サイクルとなっているというお話しをしましたよね。
その中で、音楽は2小節目に向かって流れて行くんです。2拍目の頭で、メヌエットのステップは前に進む動きをするからです。

これを知っているだけでも、フレーズ感のあるメヌエットを演奏できそうな気がしますね!
メヌエットの中に入ってるトリオってなんなわけ?
メヌエットがどんなものだったかなんとなくわかってきたところで、ちょっとした小ネタです。
すでに室内楽やオーケストラの楽曲の中などでメヌエットを弾いたことがある方の中には、

なんでメヌエットの中には「Trio(トリオ)」っていう部分が入ってるんだろう?
と疑問に思われている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか?
トリオって3重奏って意味ですよね。でも、実際は全然3重奏で弾かれていないじゃん!って思いませんか?
この由縁は、舞踏会でメヌエットが踊られていたときまで遡ります。
先ほど既述したように、メヌエットは舞踏会で1組ずつが踊りを披露するものでした。それを何十組のペアが踊るのです。
立ったまま踊りを待っている人たちも気の毒ですが、舞曲を演奏している音楽家たちのことを考えるとさらなる同情を禁じえませんよね。。。(笑)

確かに。。。延々と続く舞踏会、演奏が終わる気配なし。。。
そう。
そんな中、ぶっ続けで演奏を続けていると奏者も大変なことになりますよね。
そのため「トリオ」という部分をはさむことにしたんです。
当時この「トリオ」の部分では、本当に奏者が3人に減らされていました。
その3人以外の演奏家たちはトリオの部分で休憩することができたんです。
今演奏される機会のあるメヌエットの中にも、トリオがセットが現れるのはその名残です。
まとめ
いかがでしたか?
今までなんとなく演奏していたメヌエット、その歴史に少し触れてみるとより説得力のある演奏ができそうな気がしますよね。
これからメヌエットを弾く機会があれば、ぜひ記事を参考に曲を構築してみてくださいね。
スポンサーリンク
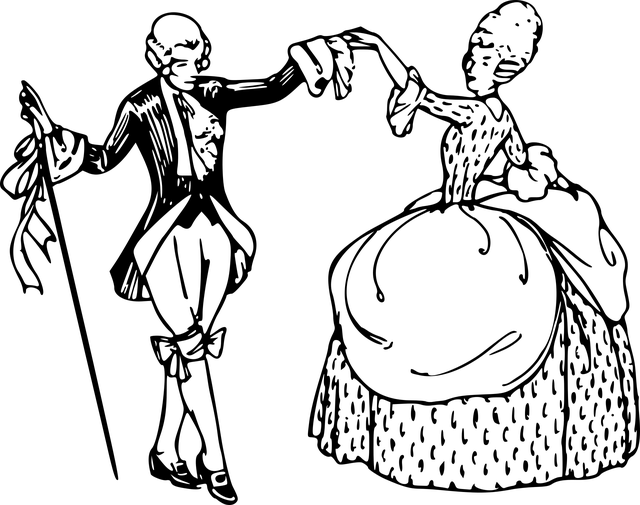


コメント
趣味でチェロを弾いています。
Youtubeに動画を上げたりしていますが、今回メヌエットのことを調べていて、ブログをみつけました。大変興味深く読ませていただき、勉強になりました。
動画の概要欄と私のブログでも、ばよりん弾きさんの記事のことをご紹介させていただきました。曲の成り立ちや背景を知ると、音楽が一層面白く感じられますね。
ありがとうございます。
ちぇっろさん
コメントありがとうございます!
バロックの曲はダンスのことを知っているともっと楽しく弾けるものが多いですよね
わたしももっともっと勉強したいと思っています