
バイオリンを上達させるために、何か画期的な練習方法はないのかしら?
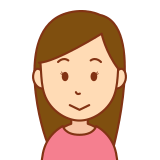
わたしの経験上、一番「効く」のは録音することだと思います。
バイオリンの練習に「録音する」方法を取り入れることについては、以前の記事にもちらりと登場させています。


録音さえすれば上達するなんて、すごく簡単ですね!早速やってみます!
いえいえ、待ってください!
この「録音する」という練習方法は、思ったより集中力を必要とするものなんです。

ただ弾いて、録音して、聞けばいいというわけではないのですね!
その通り!
今回は、ピヒラー先生直伝の魔法のバイオリン録音練習方法をご紹介したいと思うので、ぜひ読んでみてくださいね。
録音する練習に必要なもの
まずは当然ながら、録音する練習には録音機が必要になってきます。

録音機ですか。。スマホで録音する感じでも大丈夫なのかしら?
なにもなければ、スマホやメトロノームアプリなんかについている録音機能でも大丈夫です。ないより絶対いい!
でも、より細かい音色までチェックするのでしたら、音質よく録音できる録音機を探してみてもよいでしょう。
例えば今ユーチューブなどでクラシック系の演奏を配信している方などにも人気な、
持ち歩けるから、レッスンや学校での練習なんかも録音できてすごく便利でした!こだわるなら、さらに性能の高いマイクXZH-6と組み合わせる方法もあり。

今からわざわざ両方揃えるなら、アクセサリーパックのほうがお得かもですね。
練習で録音することの意味
そもそも、どうして練習を録音する必要があるのでしょう?
練習している音は、弾いている時にも聞こえていますよね。
それをわざわざ録音して聞き直さなければいけない意味はどこにあるのでしょう?
以前の記事にも書いたのですが、
「聞こえるのと聴くのは違う」んです。
自分で弾いている最中は、気分が高まっていたり、難しいテクニックに気を取られていて、「聞こえていない」場所がたくさんあるんです。
「あいつ、バイオリンを持ってないときはいいやつなんだけどな」
なんていうブラックジョークが横行してしまうくらい(笑)、楽器を弾いている時、人は独りよがりになってしまう危険性があるんです。
録音は、その「独りよがり」を気づかせてくれる大事な方法です。
録音したあと、バイオリンを置き、冷静になった頭で客観的に録音を聞き返してみましょう。
演奏中には聞こえなかった、音程やテンポの間違いなどが、はっきりとわかるはずだと思います。
わたしも生徒さんたちのレッスン中、ときどき録音(録画)をして、弾き終わったあと見てもらういたずらをすることがあります。
「どう?こうやって弾いたつもりだった?」
と尋ねると、みんな
「違う!こんな風に弾きたかったんじゃないよ!ここはね、もうちょっとこんな風に・・・!」
と一生懸命説明してくれます。
また、演奏中は「やっているつもりでも、それがどれだけ効果を持って外部に聞こえているか」わからない部分ってありませんか?
例えば、
「ここはリタルダンド(テンポをゆるやかに)したいな」
という場所があるとします。
自分ではリタルダンドしてるつもりでも、録音を聞いてみると
「あれっ?思ったよりゆっくりになってるように聞こえないもんなんだな。よし、じゃあもうちょっと思い切ってリタルダンドをかけてみようかな」
と、判断する材料にすることができるんです。
あとは、複数人で弾く時のバランスを聴く参考にもなりますね。
ピアノとバイオリン、2人で演奏しているとします。
2人のバランスはどうでしょうか?
バイオリンの音量が大きすぎるでしょうか?それとも、ピアノが大きすぎるでしょうか?
自分がその場を立ち上がって、客席まで走って行き、自分の演奏を聞ければいいのですが、自分で演奏している以上幽体離脱でもしない限り無理ですよね。
ライブと録音はまた違うので、ベストなのは信頼できる人に客席で聞いてもらうことです。
でも、誰もいない場合には録音機がバランスを決める手助けになってくれるでしょう。
魔法の録音と普通の録音の違い
音楽の練習に、すでに録音を取り入れている人はたくさんいると思います。

ふつうに自分の演奏を録音して、あとで聞く、で大丈夫なのでしょうか?
みなさん、きっとそうされていると思います。
わたしもピヒラー先生に出会うまではそうやって録音練習していました。
ピヒラー先生の録音練習方法が、普通と違うところ。
それはズバリ!
自分の演奏にコメントを残すことなんです!

録音にコメント?それはどういうことでしょう?
それはとってもシンプルな方法。
誰にでもできる簡単なお仕事ですよ(笑)。
必要なのは集中力だけ!
それでは、その魔法の録音方法のやり方を説明していきますね。
コメントを残す録音練習方法を説明するよ
1.録音する箇所を決める
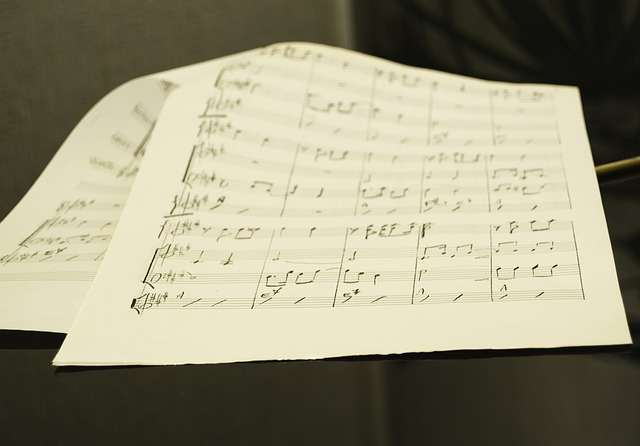
1曲通して録音するのもありですが、それは1日1回、最後の仕上げとしてだけでもよいのでは、とわたしは考えています。
まず試してほしいのは譜面1段、2段単位の少ない範囲での録音練習です。
それは、この録音練習が恐ろしいほどの集中力を要する作業だからです。
例えば
「1小節目から12小節目まで録音するぞ」
のように録音する範囲を決めてみましょう。
録音したあと、すぐ録音を止めない

録音するぞ、と決めた範囲を録音機を使って録音します。
ここまでの録音の仕方は、みなさんがいつもされている録音方法の練習と同じかもしれません。
ピヒラー先生の録音が違うのは、弾き終わったあとです。
決めた範囲を演奏し終わった後、
すぐに録音を止めないでください!
コメントを残す

決めた範囲の演奏が終わったあと、まだ録音機は回っています。
ここであなたがやるべきことは
「今の演奏で、できたこととできなかったことをコメントとして録音に残すこと」
です。
例えば、
「2小節目の音程は、いつもはうまくいかなけど今は合っていた。
3小節目の16分音符のパッセージでで右手と左手のタイミングが崩れてしまったので雑音が入ってしまった。
4小節目の音色の変化はうまく表現できたと思う。最後の重音は音がつぶれてしまった。」
のような感じで、成しえたことと、失敗したと思われる箇所を演奏と一緒に録音するのです。
少し間をおいて、聞き返す
演奏直後はまだ頭が舞い上がっているかもしれないので、すこし頭が冷えたころに録音を聞き返します。
ここでわたしがお勧めするのは「この録音は自分の演奏だ」ということを忘れる方法です。
自分への評価というのは、どうしても甘くなってしまうものなので。。
あなたは、コンクールの審査員、またはバイオリンの先生だと考えてみてください。
送られてきた、誰かの録音を評価するような、言いすぎになるかもしれませんが、ほとんど批判的な耳で、録音を聞いてみてください。
「ここは良くないな。」
「こうした方が、ずっと素敵だな」
と思う箇所を、鉛筆で書き込んでみましょう。(上級者は書き込む必要がないでしょう)
演奏が終わった後、あなた自身のコメントが残っていると思います。
あなたのコメントと、録音の内容は一致していましたか?
「合っていた」
とコメントで言っていた音程やリズムは本当に録音でも合っていたでしょうか?
なぜコメントを残すのか
勘の良い方はもうお気づきになっているかもしれません。
この「録音にコメントを残す」という練習方法はただの録音練習に加えて、「演奏中の自分の音を聴く」トレーニングにもなっているんです。
「今日は3時間も練習したぞ!」
と自信たっぷりに言える日があったとします。
でも、本当にその3時間、ずっと集中して練習したと言えるでしょうか?
弾きながら今日のお夕食は何かなー?と考えていたり、気になる人からラインが来ていないかそわそわしていたり、弾きながらテレビを見ちゃったり(笑)していなかったでしょうか?
これは、特に弾きなれた曲を練習するときに陥りがちな罠なんです。
何度も弾いている曲だから、集中していなくても体は勝手に演奏してくれます。
でも、耳が集中して演奏を聴いていなければ、練習している意味はありません。
練習に必要なのは、練習時間の長さでなく、練習の質なんです。
その練習の質を上げるのに、「練習を録音して、コメントを残す」方法はすごく効果的です。
集中して自分の演奏をつぶさに聞いていないと、「自分が演奏中に何をして、どこがうまくいってどこを失敗したか」コメントに残すことはできません。
はじめは自分のコメントと実際の録音内容が大きく異なっていることが多いかもしれません。
でも、だんだんこの練習を重ねるうちに、コメントと録音内容が一致してくることに気づくでしょう。
そして、いつか何度も連続してコメントと録音内容が一致してくる日が訪れると思います。
それは、あなたが「演奏中に冷静な頭で、集中して客観的に自分の演奏を聴けるようになった」という証拠です。
ここまでくると、毎回録音機を使用しなくても、自分の耳で自分の演奏を判断できるようになってきたと言えるのではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
わたしは書いていて、どんどん落ち込んできてしまいました(笑)。
わかっていても、なかなか毎日できることではないので。。
ただ、自信をもって言えるのは、この練習方法は確実に効果がでる方法だということです。
すぐに始められることですので、だまされたと思って!まず初めてみてはいかがでしょうか?
うまく効果が出たら、ぜひ教えてくださいね~。



コメント