「四季」などで有名なビバルディ、「G線上のアリア」などで有名なバッハ。
彼らが作曲を行っていた時代を、後世の人々は「バロック時代」と呼んでいます。
バロック時代の曲って、澄んでいて独特の響きがありますよね。

前から気になっていたんですけど、バロック時代の曲にビブラートってかけたほうがいいんですか?
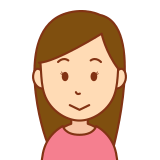
それ、迷う人多いみたいですね!
確かに20世紀前半には「バロック時代の曲にはビブラートはかけない」っていう考えが主流でした。
でも現代においては、16世紀にはすでにビブラートという技術があったということがわかっているんですよ。

せ、戦国時代にすでにビブラートが。。。
今日は、意外に歴史の深い「バロック時代のビブラート」についてお話ししたいと思います。
バロック時代のビブラートとトレモロ
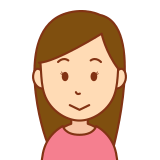
ビブラートってどんなものかわかる?

えっ?ビブラートって左手をゆすって音を震わせるあれ以外に何かあるんですか?
って思いますよね!
でも、実はビブラートって19世紀になるまで、今わたしたちが知っている「ビブラート」のことを指しているわけではなかったみたいなんです。

それでは、当時のビブラートとはどういう技術だったんですか?
そもそも17、18世紀には「ビブラート」という言葉自体がほとんど使われていませんでした。
ビブラートに近い言葉としては、1756年に作曲家&音楽教師であるWilliam Tans’ur (ウィリアム・タンシュール)が音楽辞典の中で
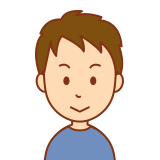
「バイブレーション」(Vibration)とは「震える音」(Trembling sound)のことだよ。
と書いています。
1778年には作曲家&音楽理論家のGeorg Joseph Vogler(ゲオルグ・ヨーゼフ・フォーグラー)が本の中で
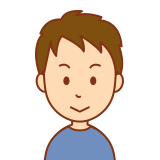
右の前腕の動きを「Wälschen Vibrato」(ローマ人のビブラート)というよ。
とも書いています。

えっ?ちょっと待ってください!
右腕の動き?
ビブラートかけるのって左手ですよね?
右手で音を震わせるのって、トレモロじゃないですか?
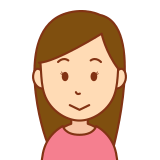
そうなんです。当時は、今日のトレモロのことをビブラートと表現していたんですね。

では、今日のビブラートは当時はなんと呼ばれていたんでしょう?
その答えは、あの有名なモーツァルトのお父さん、レオポルド・モーツァルトが書いた素晴らしい本、「バイオリン奏法」の中に見ることができます。
レオポルド・モーツァルトは
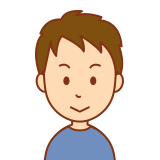
弦や鐘を強く打つと、打った音の波動が聞こえるよね。
この震える余韻がトレモロなんだよ。
と説明しています。

震える余韻て、それビブラートじゃん!
え?当時はビブラートのこと、トレモロって言っていたんですか?
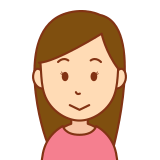
そうなんですー。
バロック時代では、ビブラートとトレモロが、今とは反対の意味だったんですね。
ちょっとややこしいですね!
ごっちゃにならないように気を付けましょう。
左手のビブラート
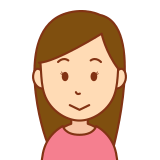
先ほどビブラートをかけるのは「左手」だとおっしゃっていましたが、実はそうとも限らないんですよ。

えー!じゃあ右手のビブラートがあるんですか?
そうなんです。
でもその話は次の章にとっておいて、とりあえずこの章ではバロック時代の左手のビブラートのお話しをしましょう。
冒頭で、日本の戦国時代にはすでにビブラートが存在していたというお話しをしました。
Sylvestro Ganassi(シルベストロ・ガナッシ)という、ヴィオラ・ダ・ガンバ&バロックフルート奏者は1542年にヴィオラ・ダ・ガンバについての論文でビブラートについて書いています。
イギリスのミュージシャン、Christopher Simpson(クリストファー―・シンプソン)は1659年にClose-shakeという「指を振動させて音を震わせる」 技術について彼の著書で示しています。
Francesco Geminiani(フランチェスコ・ジェミニアーニ)は彼の著書「The Art of Playing on the Violin」(1756-1757)でビブラートのかけ方について詳しく示しています。
ちなみにジェミニアーニのこの本は「バロックのヴァイオリン奏法」というタイトルで日本語にも訳されています。
興味がある人は読んでみるとよいでしょう。
さきほどご紹介したモーツァルトのパパ、Leopod Mozart(レオポルド・モーツァルト)も、彼の著書「バイオリン奏法」のトレモロの章で(笑)どういう風にビブラートをかけるべきか図解してわかりやすく書いてくれています。
彼の本は、バイオリンを練習している人、教えている人は必読といっても過言じゃないんじゃないかな。

作曲家はどこに左手のビブラートをかけるべきか、書いておいてくれたんでしょうか?
通常は左手のビブラートをかける場所については、特に記載はなかったようです。
ただし、Giovanni Martini(ジョヴァンニ・マルティーニ)、Francesco Maria Veracini(フランチェスコ・マリア・ヴェラチーニ), F. Couperin(フランソワ・クープラン)、 J. S. Bach (ヨハン・セバスティアン・バッハ)は、楽譜の上に波印でビブラートをかける場所を示していることもあります。
その波印はバッハの「無伴奏ソナタとパルティータ」を弾いたことがある人なら、目にしたことがある人もいるかもしれませんね。
トリルと混同されがちなのですが、ビブラートの印なので覚えておきましょうね。
バロック時代の左手のビブラートはどんなものだった?

現在では、「手首のビブラート」や「肘のビブラート」など、ビブラートにいろいろ種類がありますよね。
当時はどうだったんでしょう。
バロック時代の左手のビブラートには、手首のビブラートしか存在しませんでした。
当時はバイオリンに、肩当てもアゴ当てもついていませんでした。

確かに肩当てアゴ当てなしで、肘のビブラートをかけてしまうと、楽器への振動が強すぎてガックガクになりますね!
現在では多くの人に用いられている肘のビブラートは、実は歴史の浅い技術だったんですね。
右手のビブラート[弓のビブラート]
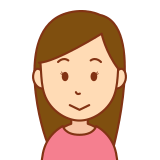
それでは、さきほどちらっとお話しした右手のビブラートのお話しをしましょうか!
正式には右手のビブラートでなく、弓のビブラートと言いますよ。

本番などで緊張して右手が震えた場合、ガタガタと弓が震えるあれでしょうか?
震える、ではなくて震わすです!(笑)
弓のビブラートは一弓の中で何度も右手を細かく突くように動かして震えるような音を出すテクニックです。
突く強さによって、その音をより強く印象的に聞かせたり、柔らかく聞かせたりすることができるんですよ。
弓のビブラートは17世紀の初めごろから使われていたことが確認されています。
左手のビブラートと違って、右手のビブラートは楽譜に記載されていることが普通でした。
同じ音をスラーでいくつもつなげて書いてあったり、TremoloやTremulant.と書いてある箇所が右手のビブラートを使う場所です。
まとめ
今回お話ししたようなことがわかってきてから、バロック時代の音楽にもビブラートを用いて演奏することが普通になってきました。
どんなビブラートをどのくらいかけるのか、というのは演奏家の曲の解釈と趣味の良さにかかってきます。
ビブラートの技術を磨いて、楽しんでバロック音楽を弾いていきましょうね。



コメント