今日のレッスン内で、生徒さんのお母さまから

バイオリンの弓ってどの辺りで弾けばよいのでしょう
という質問を頂きました。
厳密に言えば、表現したい音によって「ありとあらゆるところを弾く」というのが正解のような気がします(笑)。

えー?どこでもいいってことですか?
いえいえ、どこでもいいというわけではないんです。
ざっくり言うと、その時自分が求めている音色を作りやすい場所を弾くのが得策といえばわかりやすいでしょうか?
今日はバイオリンにおいて、弓がどんな時にどんな場所を弾くかについてお話ししていきたいと思います。
スポンサーリンク
初心者さんはまず真ん中を弾けるように
さきほど「ありとあらゆるところを弾く」と言いました。
これは特に大げさな表現ではないと思います。
バイオリンの一般的に「弓で弾く」場所を見てみましょうか。


スポンサーリンク
指板の近くを弾く

指板の近くは、駒の近くと比べて張力が少なく、弱い力でも音が鳴りやすい場所です。
初心者の方では、指板と駒の真ん中を一生懸命弾いているつもりなのにいつの間にか指板の方にすーっと弓が流れてきてしまう方も多いです。
本当は指板の近くを弾きたくないのに、弓が流れてきてしまう人は、鏡を見ながら正しい位置で弾く練習をしましょう。

指板の近くで弾くのは間違いということなのでしょうか?
いえいえ!
さきほど「弓にもポジションがある」と言ったように、指板の近くで弾いた方が理想的な音が出るシチュエーションもあるんです。
それは、ふんわり優しい音色を出したいときだったり、空気をたっぷり含んだささやくような音色を求めるときだったりします。
基本的には、
これらのタイプの音色を表現したいときは、指板周辺を探mしてみるとよいでしょう。
避けるべきなのは、無意識に張力が弱い指板の方に弓が流れていってしまうことです。
自分が頭の中に思い描いている音色があって、それを表現するために敢えて指板の近くを弓で弾くことは表現の引き出しの一つとしてとても有効です。
Sul Tasto(スル・タスト)
オーケストラなどでバイオリンを弾いている人は、この指示を目にしたことがあるのではないでしょうか?
駒の近くを弾く

駒の近くは弦の張力が強く、熟練した人でも弓のコントロールがとても難しい場所です。
バイオリンを始めたばかりの人が駒の周辺を弾こうとすると、「ガサガサ」「ギリギリ」という雑音が鳴ってしまうことでしょう。
この雑音現象についてはこちらの記事でも紹介しています。

バイオリン初心者さんの多くが、無意識に張力の弱い指板の方に弓を流していくのですが、中には駒の方に弓が流れていってしまう方もいらっしゃいます。
音がスカスカ、ガサガサしていたら、鏡を確認して駒の近くを弾いていないか確認してみましょう。

でも、駒の近くで弾いた方がよいというシチュエーションもあるということですよね。
そうなんです。
駒の近くは張力が強いので、美しい音を出すバランスが難しいのですが、弓の速度と圧力をコントロールさえできれば、強く輝くような音を出すことができます。
こういったタイプの音色を求める箇所では、敢えて駒の近くで弾くと効果的です。
ただし、先ほども述べたように駒の近くでは弓のコントロールが難しく雑音が鳴りがちなので、
自分で出している音を耳でよく聞いて、雑音にならないギリギリのところを攻めていく必要があります。
駒の近くでは、弓の圧力と速度に気を配りましょう。
圧力は強めである必要があるでしょう。
弓の速度は
・すばやいパターン
・じっくりゆっくり弾くパターン
両方があると思います。
弓の速度と圧力は、バランスが命です。
雑音が出てしまったり、弓が弦の張力で弾き飛ばされてしまう場合は、速度と圧力のバランスが崩れています。
よく聞いて試行錯誤し、自分なりのバランスを見つけ出しましょう。
Sul Ponticello(スル・ポンティチェロ)

こちらもSul Tasto(スル・タスト)同様、特別な音色を出す目的で用いられる奏法です。
スル・ポンティチェロとは「駒の上で」という意味です。
先ほども申し上げたように、駒周辺は弦の張力が強く、普通に弾いてしまうとガサガサした音になってしまいます。
このガサガサ具合を、敢えて音色として利用するのがスル・ポンティチェロです。
でも「駒の上」と言っても、馬鹿正直に「駒の真上」でなく「駒に限りなく近い場所」を弾くことが多いかもしれません。
駒の真上は、コントロール効かなくて弓があちらこちらに流れてしまいますからね(笑)。
スル・ポンティチェロと書いている場所はもちろん、自分で「ここはスル・ポンティチェロの音色を出したいな」と思う箇所があれば、実行してみると良いでしょう。
スル・ポンティチェロを利用するときは
を表現したいときに用いると良いでしょう。
スル・タスト同様多用しすぎると「単に雑音の多い人」扱いされてしまう危険があるので、自覚を持って効果的に使うことが大切です。
駒の後ろを弾く

こちらはもう特殊奏法ですね。
本来は弾く場所ではない、駒の後ろを演奏します。
現代音楽やタンゴなどで、特別な音色を求められた時に弾かれる場所です。
駒の後ろでは、もはや音程は鳴りません。
鳴るのは「キキキ」「ギギギ」という、一見雑音にしか聞こえないような音だけです。
この音を短く組み合わせてリズムを作り、打楽器のような効果を出したり、現代曲で効果音のように使用されたりします。
弓の様々なポジションをミックスする
上記の弓のポジションをすべて習得したら、あとは様々な弓のポジションをミックスしてみることも可能です。
これは中~上級者向けのテクニックかな?

弓のポジションをミックスとは、具体的にどういうことでしょう?
例えば、D,A,E3本の弦を同時に弾くときにEの弦だけを特に目立たせたい場合。
E線は普通に弾いていても際立ちますが、さらに目立たせたい場合は弓をわざと斜めに配置してD,A線を指板寄り、E線だけ駒寄りを弾いたりします。
駒の近くの方が音が輝きますから、この弓のポジションの配置だけで自動的にE線が特に際立つというわけです。
また、徐々に弓のポジションを変えていく目的で弓を斜めに配置するテクニックもあります。
例えば、フォルテからピアノにダウンボウで移行していくとき。

弓を駒の近くから指板の近くに斜めに移動させていくと、滑らかに音色と音量を変化させることができます。
もちろん、その逆でピアノからフォルテに移行するときにも使えます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
バイオリンをはじめて間もない時は「弓真ん中で、まっすぐ!」と先生に言われ続ける日々かもしれません。
でも弓には本来こんなにたくさんのポジションがあって、音色によって使い分けることができるんですね。
是非いろんな場所を弾いて、その音色の違いを実感し、楽しんでみてみてくださいね。
スポンサーリンク

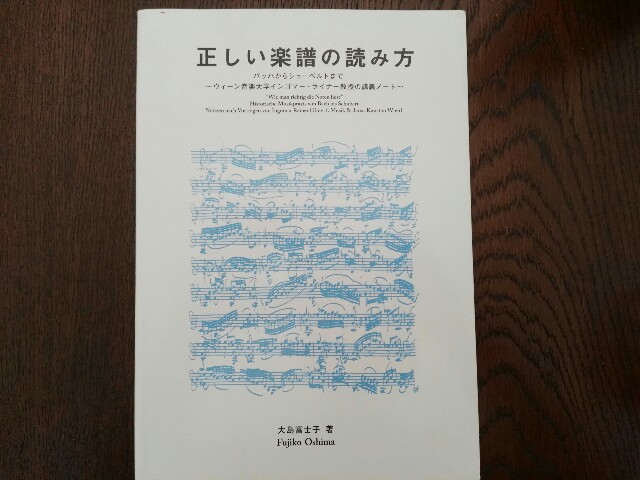
コメント