スズキバイオリン教本や新しいバイオリン教本も2巻まで進んでくると、テクニック的にも音楽的にも難解な曲が出てきますよね。
そうそう、今日は6歳の女の子がレッスンで、スズキバイオリン教本の2巻の中に入っている「リュリのガボット」の素晴らしい演奏を聞かせてくれたんです💛
ところが、曲の中に出てくるトリルを聞いたとき、わたしは一瞬迷うことに。
17世紀後半のバロック音楽の曲のトリルは、基本書いている音の1音上から始まります。
(イタリアや南ドイツなどの国ではそうでないこともアリ。)
でもリュリの曲ってどうなんだろうー。
この人1632年生まれだし。
微妙w
と思って、リュリのガボットが作曲された年代を調べてみようとしたんです。
そしたら。。。。
・・・は?
・・・・・この曲・・・・。
リュリ作曲じゃないし。
ガボットでもないし。
思わず目が点になりました。
で、リュリってだれなの?
さて、そもそもこの曲の作曲者に祭り上げられてしまっているリュリとはどんな人物なんでしょう?
ジャン=バティスト・リュリ(Jean-Baptiste [de] Lully 1632-1687)は、フランスで活躍したバロック音楽の作曲家です。
もともとはイタリア人だったのですが、1661年にルイ14世が親政を開始し、王の宮廷音楽監督に任命されたことをきっかけにフランス国籍を取得しました。
生まれはフィレンツェの粉ひき小屋の家庭で、当初音楽はほぼ独学だったということ!
フランスに行って、その才能を認められてやっと正式な音楽教育を受けたというのですから、もう隠しきれない才能にあふれまくっていたということになりますね。
太陽王と呼ばれたルイ14世にたくさんの曲を作り、その寵愛を受けたリュリ。
王様と一緒に踊り手として舞台に立ったこともあったそうです。

リュリって大成功した作曲家だったんですね!
でも、スズキ教本や新しいバイオリン教本のガボットって彼の曲じゃなかったんですか?
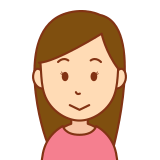
そうなんです!
この曲、本当はマラン・マレ(Marin Marais)が書いたヴィオラ・ダ・ガンバ集第1巻「組曲第2ニ短調」の24曲目のロンドだそうですよ!
マラン・マレってどんな作曲家?
マラン・マレ(Marin Marais 1656 - 1728)はフランスの作曲者、指揮者、そしてヴィオラ・ダ・ガンバ奏者です。
マレは靴職人の質素な家庭に生まれました。
1666年には、叔父が司祭を務めていた教会の聖歌隊員となります。
聖歌隊に所属していたときには、すでにヴィオラ・ダ・ガンバを習っていたと考えられているマレですが、1672年に声を壊して聖歌隊を辞めざるを得なくなってから、本格的に当時最も有名な奏者であったニコラ・ホットマンとムッシュ・ド・サントコロンブにヴィオラ・ダ・ガンバを習うことになったそうです。
マレはリュリの高い評価を受けており、リュリの主要なオペラの公演にガンバ奏者として参加していました。マレはリュリを作曲の師匠と仰いでいたそうです。
リュリの死後、イタリア音楽の表現と方式をフランス音楽に取り入れるべきかという、「音楽戦争」が勃発しました。
多くのフランス作曲家はスタイルの融合を実験的に試みましたが、マレは伝統主義者の一人として、その融合を拒否しました。
その頑固ぶりは、イタリア語とされていた「ソナタ」を生徒に弾かせることさえ禁じていたほどだったそうです!
マレはフランスの韻律に合わせた明快な旋律を大切にし、師であるリュリの歩んできた道を厳守しました。
その結果、彼のオペラはリュリのオペラ同様大成功し、1705年には国王の推薦により、王立音楽院オーケストラのディレクターに任命されました。

マレも師匠リュリと同様成功した音楽家だったんですね!
時代や国が一緒で、さらに子弟ということで共通点が多い2人だったから、混同されて曲が間違われちゃったのかもしれませんね。
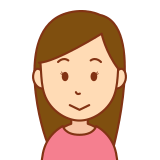
そうね。そもそもは1907年にドイツのバイオリニスト、ウィリー・ブルメスター(Willy Burmester)が、マレのロンドをバイオリン用にアレンジしたときに、間違ってリュリのガボットの編曲として発表してしまったそうよ。
その曲を鈴木バイオリン教本の鈴木鎮一先生がベルリンで聴いて、リュリの曲と思ってしまったというわけ。

ウィリーさん、やっちゃいましたね(汗)
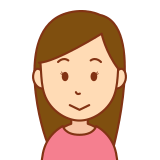
まあ、昔の曲の作曲者が誤解されて、後から訂正されることって結構あることだから、仕方ないことではあるかなあ。

確かに!例えばハイドンのセレナーデカルテットとか!あれは実はハイドンじゃなくて、ホフシュテッター作って言われてますもんね。
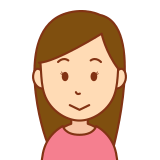
そうそう。
誤解、訂正は仕方ないけど、大事なのは、正しい作曲者や曲のタイトルが判明したら、それをわかっておくことなんじゃないかな。
それは演奏の上でとても大切なヒントになるからね。
マレのロンドを聞いてみよう
それでは、リュリのガボットと誤解されているマレのロンドを聞いてみましょう。
ヴィオラ・ダ・ガンバの音を聞いたことがない人は、ガンバのやさしい音色を楽しんで聞いてくださいね。

めっちゃ「リュリのガボット」ですね。
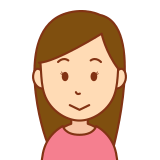
だから(笑)マレのロンドなんだってば!(笑)
作品の作曲者やタイトルは結構大事
最新版のスズキ教本や新しいバイオリン教本には、「この曲はやっぱりマレのものでしたよ」って注釈がついているのでしょうか?
私は古い版しか持っていないので、今度生徒さんに聞いてみようと思います。
さっきも言ったように、作曲者やタイトルというのは楽曲を知るうえで、大切な情報になってくれるからとても重要だと思うんです。
例えば、マレのロンドの楽譜を見れば、音楽をやっている人ならば「これはバロックの曲だろうな」とたいていの人が気づきます。
でも、
作曲者がどこの国の人だったか
何年に作られた作品だったか
などの違いで、装飾音の付け方がかわってきたり、演奏法が変化したりすることがあるはずなんです。
トリル一つをとってみても、
「リュリの曲だったら、ちょうど17世紀中盤だから、、、うーん、トリルはそれでも上からかけてただろうな、、、ただ、ここはちょうど1つ前の音がCだから、やっぱりオリジナルの音からかけてもいいかな。。。」
と考察するのですが、マレならばすでに17世紀後半の作曲家なので、その時にはトリルが上からというのはすでに一部の国の例外を除いて一般的になっていました。
だから、どのようなトリルをかけたらよいからは、音楽的な流れからのみ判断すればよいことになるでしょう。

タイトルもそんなに大事でしょうか?
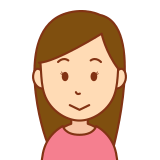
その曲を深く知るという意味では、重要な情報源になりうるはずですよ。
例えば、新しいバイオリン教本の2巻、42番に入っている「わかれ」という曲。
この曲をレッスンしていたとき、わたしの頭の中が一度「?」で覆いつくされたことがあるんです。
そのお話はこちらでご覧いただけますので、よろしければどうぞー♪

と、いうわけでスズキバイオリン教本や新しいバイオリン教本の2巻で、リュリのガボットを弾くことになった人は
「この曲はリュリのガボットじゃなくて、マレのロンド!」
という雑学で先生と盛り上がってみてくださいねー。
それでは、みんな練習頑張っていきましょう!



コメント